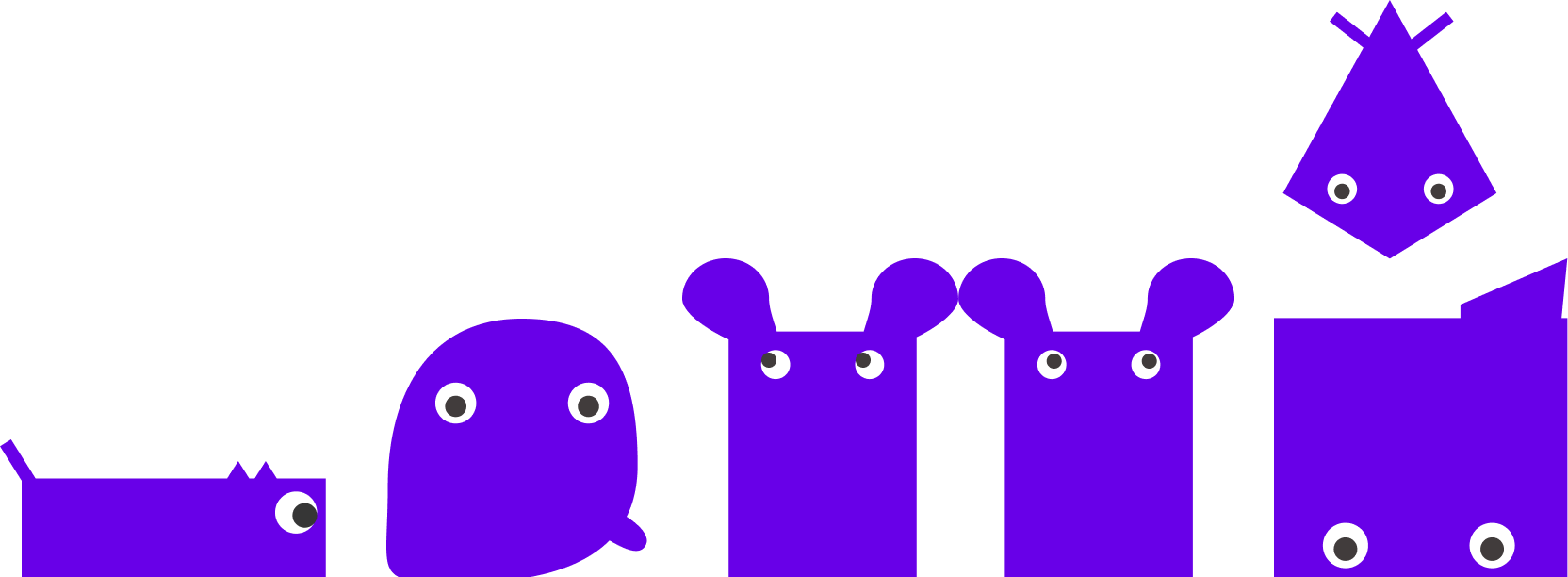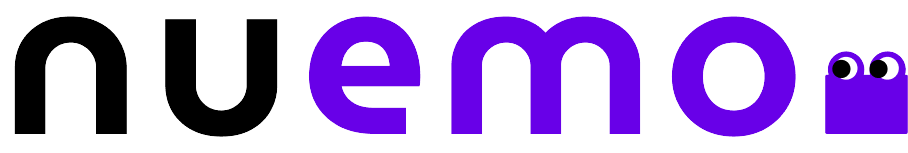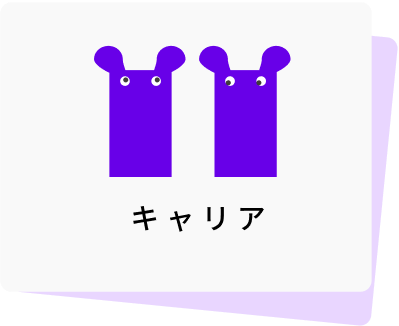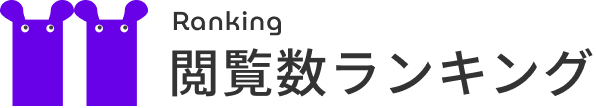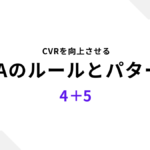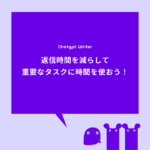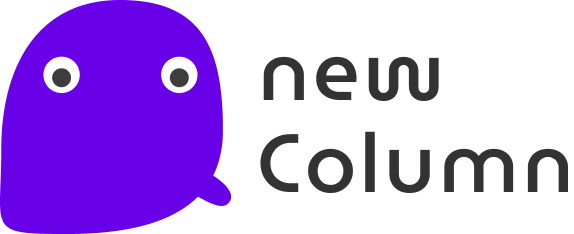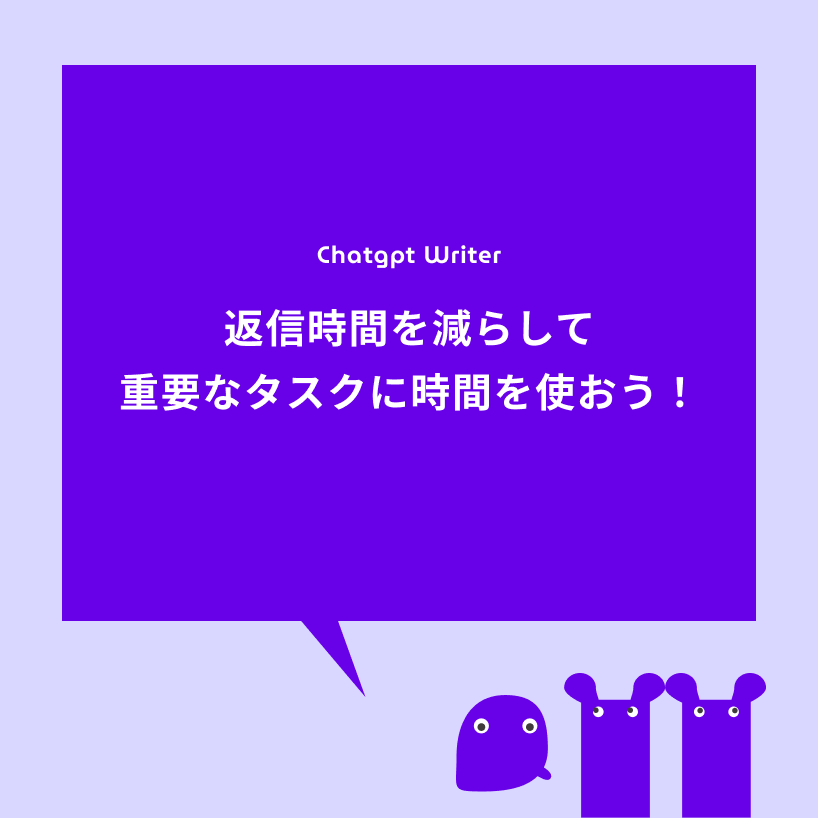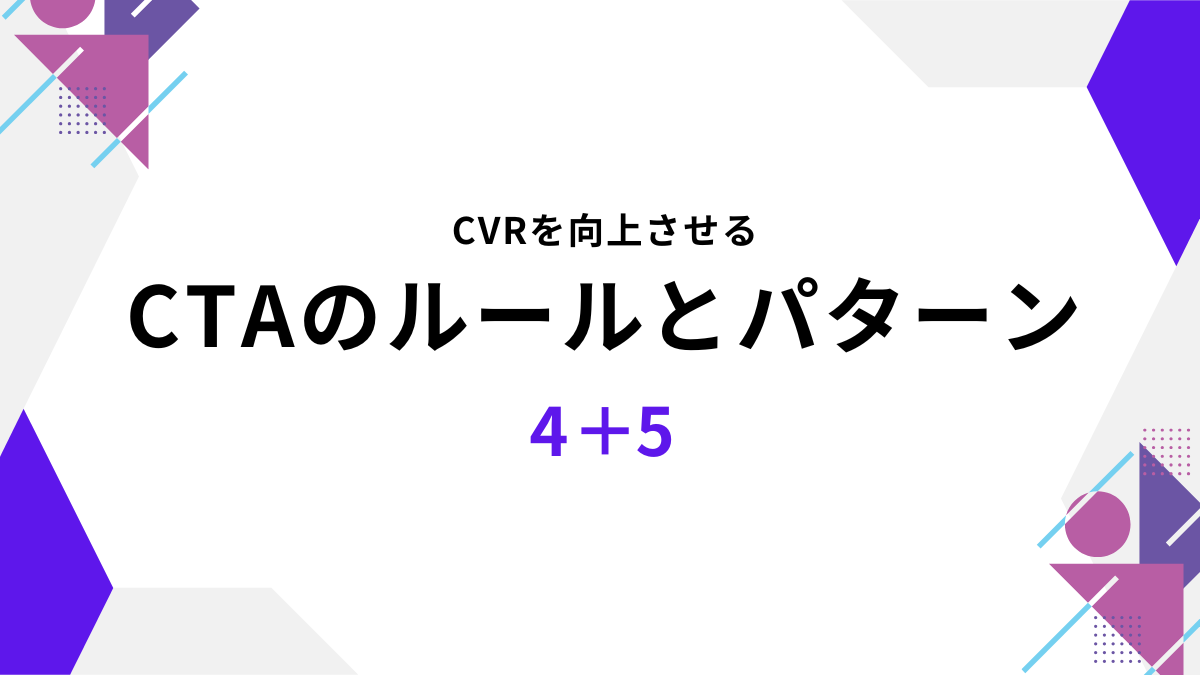WEBサイトを改善!見出しやコンテンツ変更による施策例を7つ紹介
WEBサイトを制作する立場として、「できる限りお客様に貢献したい」と考えるはず。
しかし、一発で正解を出せるデザイナーやマーケターは少ないでしょう。
誰でも簡単にCVRが高く、SEO流入も稼げるサイトを作ることは、難易度が高いです。
そこで、WEBサイトを改善する・運用するという思考が大切になります。
今回はWEBサイト改善における「見出し・コンテンツ」の目線から、どこを改善すべきかを紹介します。
見出し・コンテンツを改善するとは、そもそも何を変えるのか?
今回は数ある改善箇所の中から「見出し・コンテンツ編」として紹介します。
見出しはみなさんもお分かりかと思います。
例えば、いわゆる「キャッチコピー」や「hタグ要素」がそれに当たります。
このコラムでも、見出しが使われています。
このセクションの見出しは「見出し・コンテンツを改善するとは、そもそも何を変えるのか?」の部分ですね。
人間がWEBサイトを確認するとき、最初から詳細な文章を読むことは少ないです。
みなさんも、ある程度見出しやキャッチコピー、画像要素を見て当たりを付け、気になった箇所をよく読むはず。
つまり、WEBサイトにおいては、見出しやキャッチコピー要素は非常に重要な要素なのです。
それでは、コンテンツとは何か?
では、コンテンツを改善する、とは何を指すのでしょうか?
ここでいうコンテンツとは、以下のようなことを指します。
・ページや情報が適切に掲載されているか?
・ページの長さは正しいのか?
・言葉遣いや表現方法は正しいのか?
・画像とコンテンツの組み合わせは正しいのか?
上記を指します。
例えば、優しい雰囲気のサイトなのに、堅苦しい言葉遣いだとトンマナに合わないですよね?
逆に優しい雰囲気のサイトで優しい言葉遣いだったのに、ターゲットからは受け入れられていないこともあります。
それを思い切ってテストして、どちらがより好まれるのか?を探ることが、WEBサイト改善のポイントになります。
見出し・コンテンツで変えるべきポイント7選
それでは、本題です。
見出しやコンテンツを改善する際に、どの部分を変えるのか?
改善ポイントを7つ紹介します。
改善ポイント①見出し・キャッチコピーの表現を変更する
まずは見出しの表現です。
例えば、営業代行会社の例を見ていきます。
「信頼のおける報告体制でクレームの少ない営業代行を」というキャッチコピーを制作時に作っていました。
しかし、あまり反応が良くない・・・ということで、大胆に変更します。
「1アポ○○円でオプション料金無し!安心価格の営業代行」
上記は信頼感よりもお得感を打ち出すコピーですね。
それぞれのCVRや反応率、スクロール率をA/Bテストしてみると、違った結果が生まれるはずです。
また、各見出し要素も細かく変更し、それぞれの組み合わせを多変量テストしてみると、一番良い組み合わせを発見することができます。
見出しは最も読まれやすい箇所なので、逐一テストしておきたいですね。
改善ポイント②見出し・キャッチフレーズは長い?短い?
見出しやキャッチフレーズが長すぎないか?を見ておきましょう。
見出しやキャッチフレーズは短ければ短いほど良いという定説があります。
例えば、Appleの有名な例があります。
Appleは従来、広告でマシンの機能紹介をずらーっと並べたクリエイティブを採用していました。
その当時は全くMacは売れなかったそうです。
しかし、スティーブ・ジョブズは圧倒的にキャッチフレーズをスリム化します。
「Think different」のたった一言でキャッチコピーを変更させたところ、Macは急激に売れるようになったのです。
もちろん、適当に短くすれば良いわけではありません。
使っている人の姿を想像して、そこに刺さるコピーを考える必要がありますね。
キャッチコピーの長さについても、定期的に見直してテストをしてみましょう。
改善ポイント③どんな長さのページが良いか?スクロールor遷移で好みを図る
コンテンツの観点ですが、1ページの長さもCVRに影響します。
1ページに情報を詰め込んだほうが良い場合もありますし、ページを分散してメニューごとに切り分けたほうが良いパターンもあります。
これは、テストの対象です。
例えば、サービスが10個あるとして、それらを1ページに羅列していたとします。
ここで仮説が生まれます。
「サービスを10個羅列していてもユーザーは情報量が多すぎて読まず、離脱されているのではないか?」
この仮説を検証するために、サービスページを10個分作り、トップページではメニューを配置する形に変更。
その変更を行ったところ、流入数も増加し、離脱率も減少しました。
仮説は正しかったということですね。
ただ、ユーザーの属性によっては、1ページに全部まとまっていたほうが良い場合もあります。
サービスが10個は極端な例ですが、例えば2つしか無いのであれば、1ページにまとめても問題ないかもしれません。
これはテストを行ってみて、正解を見つける作業になりそうですね。
改善ポイント④普通の文章or箇条書きリスト型式でテスト
商品詳細ページやサービス詳細ページは、どうしても長文で表現する必要がある場合が多いです。
しかし、長文はなかなか読まれづらい傾向にあります。
そこで、「この長文の要点だけまとめて、箇条書きにしてみる」という方法があります。
ユーザーは普通の文章を読むのは大変ですが、箇条書きリストは分かりやすく、精読率が上がることがあります。
もちろん、テストを行う必要がありますが、長文が続いてユーザーが疲れている可能性がある場合は、テストを行ってみましょう。
ここで、注意点があります。
たしかに長文を箇条書きにすると、要点がまとまって読みやすくなります。
ただ、そこまで情報量が多くない場合は、スッキリしすぎてユーザーが知りたい情報を削ぎ落としてしまう場合もあるのです。
また、重要な情報を箇条書きにするのは良いですが、SEO用に配置している文章がある場合、それを箇条書きにしてもあまり意味がありません。
様々な条件のもとで、テストを行う必要がありそうですね。
改善ポイント⑤フレーミング効果を実験する
フレーミング効果とは、同じ情報に対して別の焦点から発信することを指します。
例えば、継続率が40%のプロダクトがあるとします。
広告バナーに「継続率40%」と書かれていたら、どう感じるでしょうか?
40%しか継続しないのか…と考えると思います。
しかし、「3人に1人が継続リピート!」と書かれていたらどうでしょうか?
「そんなに継続しているのか〜どんな商品なのかな?」と少し期待してしまうはず。
このように同じ数字でも、別角度から切り出すことによって人の意思決定を変えることができる手法なのです。
・認知症予防に効果あり!
・今対策しないと認知症になる確率が○%!
現実では使えないコピーですが、どちらも「認知症予防を促す内容」です。
しかし、後者の「認知症になる」という負の感情のほうが、行動を促しやすい傾向にあります。
もし既存の見出しやコンテンツがメリットだけを語る内容になっていたら、フレーミング効果を試してみると良いです。
サービスを使うメリットではなく、使わないデメリットをメインコピーにすると全く別の反応になります。
こちらもA/Bテストを通して、改善していきたいですね。
改善ポイント⑥文字のフォントを大きくしたり、段落の広さを変える
文字フォントのサイズ感を変更するだけで、精読率が変わります。
また、段落の広さを整えることも離脱率やCVRに影響してくるのです。
・フォント選び(ゴシック、明朝など)
・フォントウェイト(100〜900)
・フォントの色(#000000→#333333)
・行の高さ
・フォントサイズ
基本的には長文を明朝体で記載していると、読みづらくなります。
それをゴシックに変更してみる。
また、色合いを調整したり、フォントの重さの組み合わせで読みやすさは変わるものです。
例えばWordPressのブログテーマは最初から読みやすい状況にしてありますが、実際にコーポレートサイトを制作する際は、デザイン段階で読みやすさも考慮して作成が必要ですね。
おしゃれにしすぎると、最も重要なコンテンツ部分が疎かになってしまいます。
改善ポイント⑦言葉遣いは適切か?雰囲気を変更する
サイトのトンマナやターゲットに合わせて、言葉遣いを変えてみることも大切です。
逆に、サイトのトンマナに寄せすぎている場合もあり、テストを行い比較しユーザーの反応を見てみる必要があります。
・話口調にしてみる
・真面目な口調にする
・尊敬語や謙譲語を入れてみる
ターゲットによって、様々な口調が想定されます。
ブランディングにも寄与する内容なので、言葉遣いを変更してみるとよいですね。

最近、ブランディングが上手なサイトで話題になったのは、モンブランさんです。
「愛されることは、むつかしくないよ」というコピーは、サイト自体のトンマナを考えたうえで作られたものになっています。
ターゲットや事業で大切にしている世界観などを表現するには、様々な試行錯誤も必要でしょう。
割と真面目な口調のサービスが多いため、それを崩す口調をテストし、ユーザーの反応を見てみることもサイト改善の一つのやり方だと言えるでしょう。
まとめ
今回はWEBサイトを改善するために、見出しやコンテンツ部分での改善点を紹介していきました。
WEBサイト改善では、CTA編などのコラムも紹介していますので、ぜひ参考にしていただけますと幸いです!